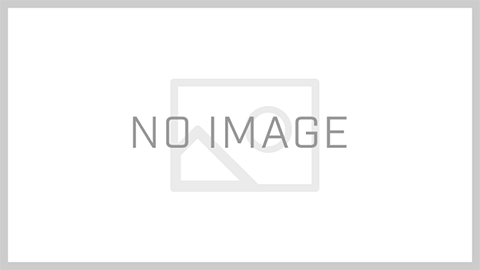[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/778615.jpg” name=”6歳の次女” type=”l icon_red “]ねぇママ。おしることぜんざいってどう違うの?[/voice]


[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/084162.jpg” name=”10歳の長女” type=”r icon_red “]おしるこは知ってるけど、ぜんざいってよくわかんないなぁ。[/voice]
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/th3V3LE27V.jpg” name=”琴子” type=”l icon_red “]・・・なんだろう?地域の呼び方の違い?汁気があるか・ないかの違い?[/voice]
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/682581-1.jpg” name=”パパ” type=”r icon_red “]パパもよくわかんないけど、こしあんか粒あんか、の違いじゃないのかなぁ?[/voice]
パパもママもわかりませんでした(;^_^A
そこで「おしるこ」と「ぜんざい」の違い、さらに関西地方でよく聞くといわれる「亀山」についてや小豆(あずき)の栄養素、意外な使い道についても家族で調べることにしました!
おしることぜんざいの違いって?
おしるこ
まず、我が家では馴染み深い、“おしるこ”から調べることに。
広辞苑にはこう記されています。
【おしるこ(お汁粉)】
小豆の餡(あん)を水で延ばして汁として砂糖を加えて煮、中に餅又は白玉などを入れたもの。こしあんのものと粒あんのものとがある。
漢字で“汁の粉”と書くことから想像できるように「おしるこ」とは汁気のあるあんこの中に、焼いたお餅や白玉が入っているものですね。
ですが、調べてみると関東と関西ではこの「おしるこ」と呼ぶものに違いがあることが判明!
[box class=”yellow_box” title=”関東のおしるこ”]
・こしあん、粒あんは関係なく、汁気が多いあんこの中にお餅が入っているもの。
※こしあんを「御前汁粉」、粒あんを「田舎汁粉」という地域もある。
[/box]
[box class=”yellow_box” title=”関西のおしるこ”]
・汁気の多いこしあんで、お餅や白玉が入っているもの。
[/box]
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/th2QSS3ONB.jpg” name=”琴子” type=”l icon_red “]関東では、こしあんでも粒あんでも、どちらでもあんこの汁気があるものが「おしるこ」。
でも、関西で「おしるこ」といえば、こしあんの汁気があるものなのね。
[/voice]
地域によって違ってくるんですね。
ではぜんざいはどうなんでしょうか??
ぜんざい
ウィキペディアにはこう記されています。
【ぜんざい(善哉)】
ぜんざい(善哉)は、主に小豆を砂糖で甘く煮て、その中に餅や白玉団子、栗の甘露煮などを入れた日本の食べ物である。
「ぜんざい」という名前の由来は、「善哉」説が有名(※諸説あります)。
ぜんざいを漢字で書くと「善哉」ですが、仏教用語で「善哉(ぜんざい・よきかな)」は「すばらしい」という意味。
トンチで有名な一休和尚が、ぜんざいを初めて食べて美味しさのあまり「善哉」と叫んだことからきている、という説があります。
そしてやはりこの「ぜんざい」も関東と関西で違いがあることがわかりました!
[box class=”blue_box” title=”関東のぜんざい”]
・白玉や焼いた餅に、汁気のないあんこを添えたもの。
[/box]
[box class=”blue_box” title=”関西のぜんざい”]
・粒あんを使った温かい汁物。焼いた餅や白玉を入れる。
[/box]
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/682595.jpg” name=”パパ” type=”l icon_red “]つまり、関東では汁気の有り無しで「おしるこ」と「ぜんざい」を区別して、関西ではこしあん・粒あんの違いで区別するということなんだね!
[/voice]
なるほど。
しかしここで新たな疑問。
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/th3V3LE27V.jpg” name=”琴子” type=”r icon_red “]「汁気のないあんこ」って関西にはないのかな?[/voice]
ということでさらに調査を続けていくと、関西には汁なしの「亀山」というものが存在していました。
くわしくみてみましょう!
関西の「亀山」って?
汁気のないあんこに餅や白玉を添えたものを関西では【亀山】と呼びます。
関東の「ぜんざい」と同じですね。
「亀山」という名前の由来は2つの説があります。
1つは地名説で、小豆の有名な産地である、丹波の亀山からきている、という説。
2つ目はお店の屋号説。岐阜県出身の亀山さんという人が、大阪で「亀山屋」というお餅屋さんを開店し粒あんを使ったぜんざいを売り出したら大人気メニューになった、という説があるといわれています。
「おしるこ」「ぜんざい」「亀山」・・・ちょっとややこしくなってきたのでまとまると以下のようになります。

出典:https://style.nikkei.com/article/DGXNASJB0702P_X01C13A1AA1P00
すると今度は、学校の社会で日本地理を習い始めた長女が・・・
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/084162.jpg” name=”10歳の長女” type=”r icon_red “]関東と関西ってどこが境目なの??[/voice]
・・・確かに。そもそもはっきりした境界線ってあるんでしょうか?
関東と関西、境界はどこ?
うどんの汁、おでんの味、うなぎの焼き方・・・他にも関東・関西で違うものっていっぱいありますよね。
関東と関西の境目については以前から様々な意見があり、明確に分けることは難しいようです。
ただ、食文化に関しては「関ケ原が境目」だとする意見が圧倒的多数でした。
今回、調べている「おしるこ」「ぜんざい」の呼び方については以下の絵のような境があります。

出典:https://matome.naver.jp/odai/2149412831720399701
[voice icon=”https://kotokochannel.com/wp-content/uploads/2018/01/082991.jpg” name=”10歳の長女” type=”r icon_red “]場所によって呼び方が変わるっておもしろいね!
夏休みの自由研究で、関東と関西の違いをいろいろ調べてみたいな♪[/voice]
洋菓子と比べると少し地味なイメージのあんこですが、家族の健康を守る母としては、小豆(あずき)の栄養・効能が気になって調べてみました。
あんこは万能な健康食品!
小豆(あずき)には、食物繊維やビタミン・ミネラルなどたくさんの栄養がつまっていることがわかりました。
[aside type=”normal”]小豆の栄養素について
・約22%は良質なたんぱく質
・食物繊維はゴボウの3倍
・ポリフェノールは赤ワインより多く含まれる
・カリウムも多いのでむくみ予防にも◎
[/aside]
小豆の歴史は古く、昔は医薬品として使われていたほどの食材なんです。
ウチの長女が便秘がちなのもあり、これからもっと気軽に食事やおやつに取り入れようと思いました♪
気軽におやつに取り入れよう!
↓シンプルな7つの工程で美味しいあんこがつくれます!
動画6分から保存方法も解説していますよ。
時間のある時に小豆を好みの甘さで煮ておき、粗熱がとれたら小分けに冷凍しておけば、アイスに添えたりしていつでも食べられますね。
煮て冷凍しておいた小豆とアイスでおやつ🎵 pic.twitter.com/hmSXFL0RXJ
— さら (@nie_ikuko) 2018年1月14日
我が家はよくパンケーキをつくるのですが、いつものメープルシロップの代わりにあんこを添えてみようと思います。
食パンにバター+あんこもいいですね!
食べる以外にも、小豆には意外な使い道があるんですよ!
次から動画やツイッターでみてみましょう。
小豆がアイピローやカイロにも♪
小豆でつくるアイピローやカイロ。レンジで温める『あずきカイロ』が寒い季節に大活躍!
パソコンやスマホで眼を酷使する方、肩凝りがつらい方におすすめです!
※用意するもの:内袋用ガーゼ、カバー用ダブルガーゼ、針と糸(またはミシン)
あずきカイロの幸せ度半端ない。
普通のカイロより湯たんぽよりすき。あずきカイロわかんない人にうまく伝えようとすると…なんだろうな…
蒸しタオルのぬくさがじんわーりもっとつづくやつ。— にろ (@26___maru) 2018年1月25日
私は、長女を出産したのが真冬だったんですが、初めての育児で授乳も最初はうまくいかず、育児疲れと緊張と寒さで肩がバッキバキに凝ってとても辛かったときに、あずきカイロで首回り~肩を暖めて乗り切った思い出があります。
ほんのりとあずきの香りがして、とても癒されましたよ。
↓こんな感じです!
小豆を買ってきて自分用にネックカイロを作りました😄レンジでチン♪して首に巻くと暖かくて気持ちいいィ〜😆🧣首のサイズに合わせてスナップも付けました(^。^)ほんのり小豆の香りして暖かいのも結構もつし、ウン❗️気に入った❣️ pic.twitter.com/aZLIV5Rntv
— JUN JUN (@handmade_junjun) 2018年1月24日
まとめ
以上、「おしることぜんざいの違いは?関西の亀山って?小豆の栄養と意外な使い方も!」をご紹介しました。
おしることぜんざい。
同じような食べ物なのに地域によって定義や呼び方が違うなんて、日本の食文化っておもしろいですよね。
おしることぜんざいの違いは、6歳の次女には少し難しかったようですが(;^_^A
この小さな粒の中にはたくさんの栄養がつまっていることもわかりましたし、アイピローやカイロにもなって本当に万能選手!
小豆をこれからもっと食卓に取り入れていこう、と思いました!